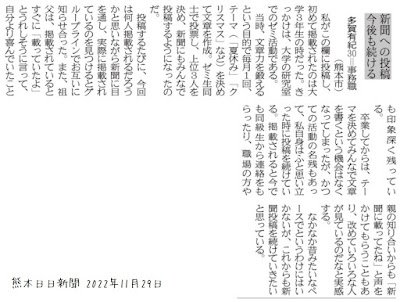14ラストゼミが終わり、気が抜けたのか、本日のガリラボは
閑散としておりました。特に午前中は誰もおらず、10:30からの
院ゼミでM1(17)多賀と山下が来るまでは誰もいない状態で、非常に
静かなガリラボでした。
院ゼミの90分の60分はほぼ雑談。今日は理論と実践というのは
いかに独立したもので相互に関係がないのかという点を、得意の
「自転車理論」を使っての雑談でした。これから理屈がわかっている
からといって授業ができるわけではないし、授業ができるからといって
授業の理屈がわかっているわけでもない。そんなことをわかるわけで、
教師というものが通常いかに実践家として(のみ)振舞っているかが
山下は理解してくれたのではないかと思います。
それ以外にもいくつか事例を出しながらの雑談でしたが、今日の雑談は
結構、いい内容ではなかったろうかと思いました。
ただ、最後に山下が、「自転車のことしか残っていない」と言っており
ました。自転車理論はかなり強い印象を与えたようです。笑
お昼、16ゼミ幹部会議。
ゼミ長:川上、副ゼミ長:笠原、会計長:小島、ガリボイス:大塚
以上が幹部の布陣なわけですが、今後の活動については色々と話を
深めていく中で、最近少し気になっていたことは話しました。
文章を書くトレーニングとしてそのまとめ役として「ガリボイス」
という幹部が必要だったのですが、最近、それが今ひとつゼミの中で
盛り上がらないように感じておりました。
方向性が少しずれてきている、またゼミ生の気持ちの中にもガリボ
イスというのは今一つマッチしていないのかもと、そういったことが
気になっていました。
その証拠に最近、「ガリボイス」というタグを通信につけることが
ほとんどありません。2017年度はほんとに少なかった。
「ガリボイス」という言葉は
OG(07)上村が命名し使い始めたものです。
16ゼミ生となると、それからもう10年近くが経っているわけで、そろ
そろ変化の時期なのかと思い、気になっていたので、「いっそのこと名前を
変えよう」と提案しておきました。
変更するとすれば、大塚が今後担当していくべき内容にマッチした名称が
いいですね。
どういった名称が良いか、宿題にしておきました。
ということで、10年近く使用してきた
ガリボイスという名称ですが、
16ゼミの代で看板を下すことになりそうです。
歴代のガリボイス担当者からクレームが来そうですが(ま、そんなことは
ないでしょうけど)、ガリボイスの後継となる新しい名称が決まったら
紹介したいと思います。
午後、キャリアセンター長の立場で企業訪問に出かけたので、ガリラボの
様子はよくわかりませんが、私が出る前に、
3年(15)八並が後輩たちにフォトショやイラレなどを
教えているようでした。
その様子をちらっと見ながら、実践共同体(Community of Practice)の良い
事例だなと思いました。
学ぶ側は具体的なツールのことを局所的に学びながらも、本人が気づかない
うちに実はもっと大きな出来事が進行しています。
情報処理実習室で作業する人、ガリラボで作業する人、色々ですが、特に
ガリラボという実践共同体に限って言うながら、両者の違いは先々、随分と
異なる成長の軌道を歩むことにつながっていくでしょう。
学びという実践は、非常に恐ろしく、怖いものです。
学びの本当に意味についてある程度理解したとき、大げさにいえばわが身の
行動について背筋が凍りそうな思いになったことを覚えています。^^;
現在M1と読んでいるテキストの「正統的周辺参加」というのは、その恐ろし
さを解明し、世の中に知らしめたものでした。